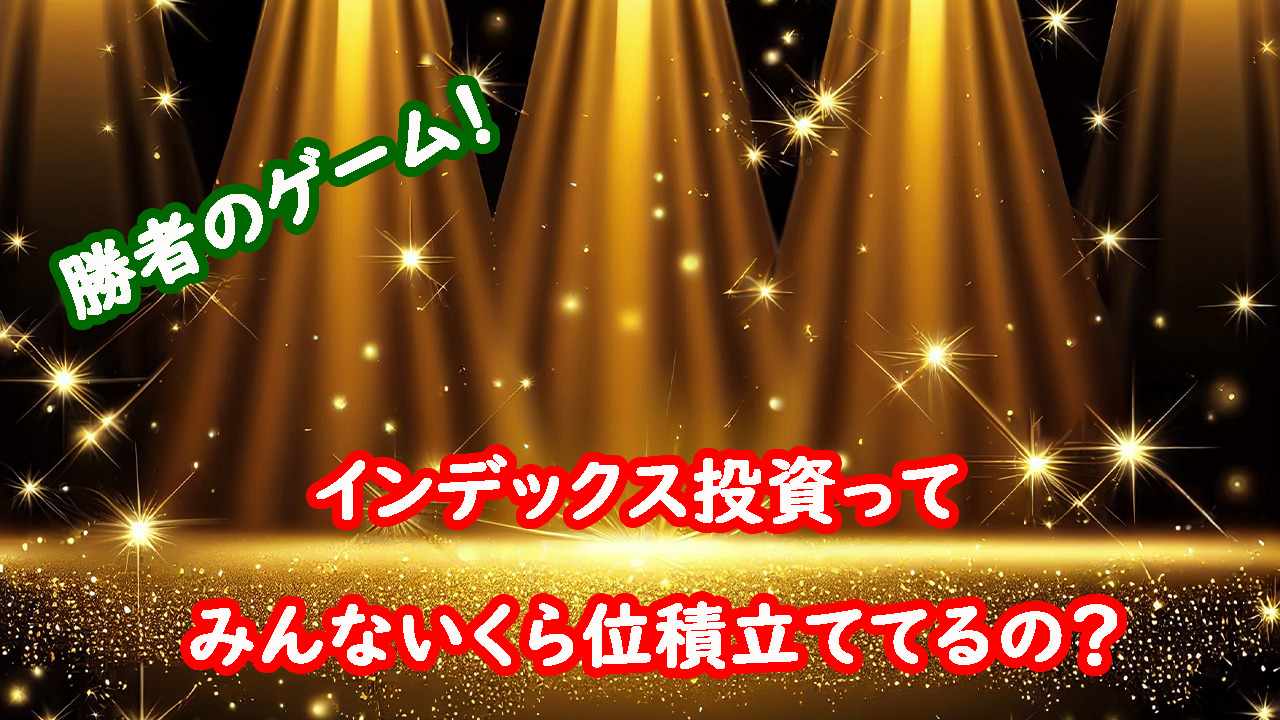【意外と大丈夫?】自己破産したら家族や仕事、生活はどうなるか?解説します!
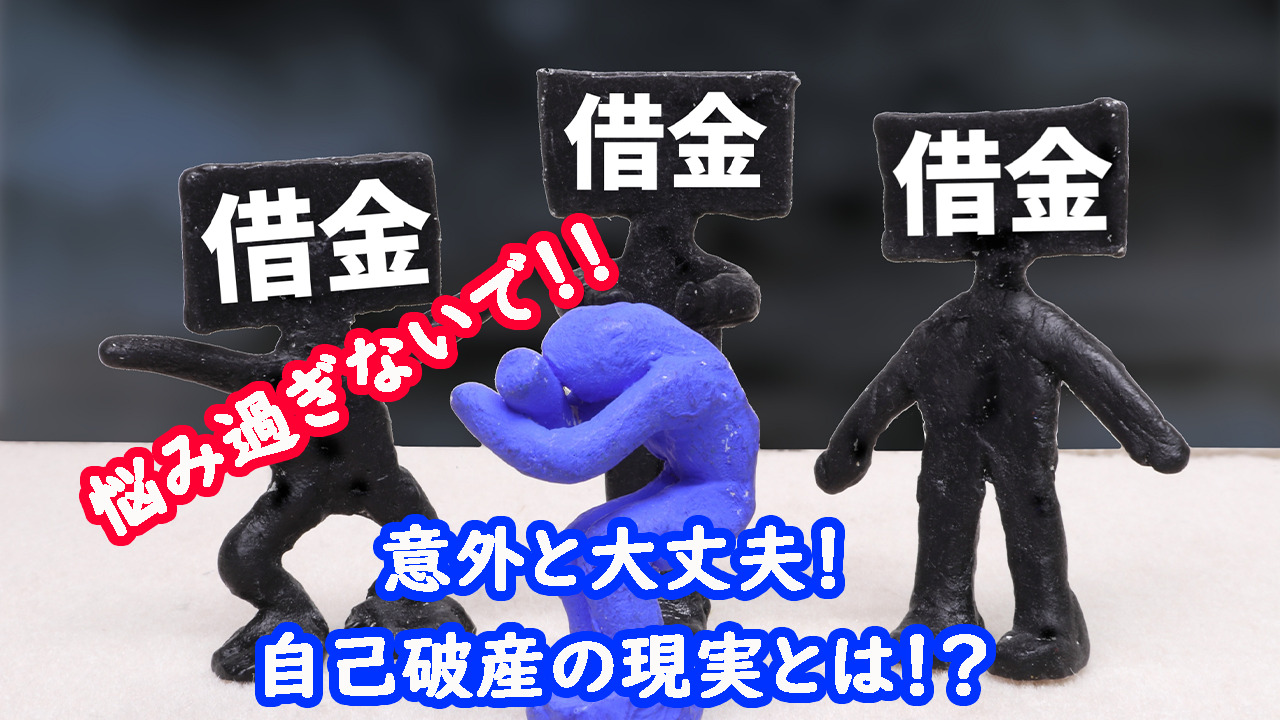
自己破産と聞くと、人生の終わりのように感じるかもしれません。
しかし、実際にはそんなことはありません。
自己破産は、借金に苦しむ人にとって、新しいスタートを切るチャンスなのです。
この記事では、自己破産が意外と何ともない理由を解説します。
人生終了みたいなイメージがあるなぁ。
まぁ、借金の督促状や電話の嵐もつらいだろうど・・・。
悩んで悩んで、借金苦で絶望している位なら、選択肢の1つとして考えるべきよね。
まぁ、そうならないように、家計をしっかりと安定させる事が一番大事だけどね❢
自己破産とは
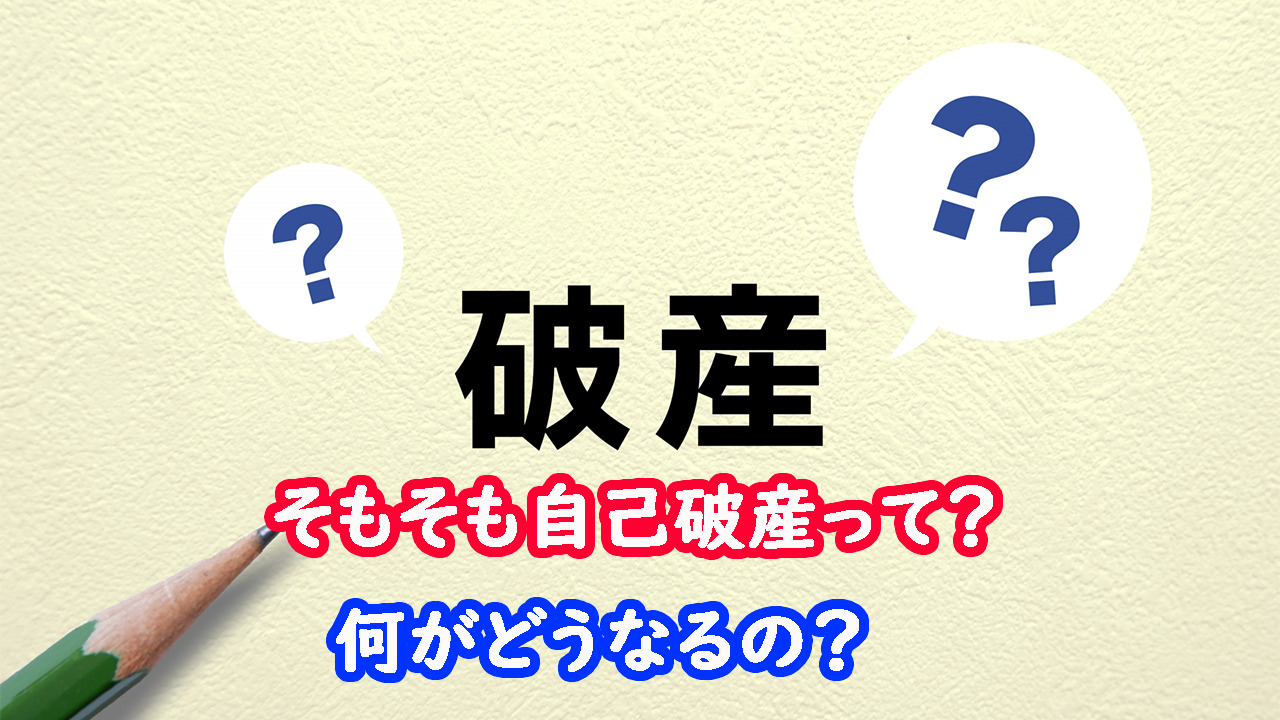
自己破産とは借金を免除してもらう手続き
自己破産とは、借金を返済できない状態に陥ったときに、裁判所に申し立てて、借金を免除してもらう手続きのことです。
自己破産をすると、借金の返済義務がなくなりますが、同時に財産のほとんどを失うことになります。
また、自己破産には一定の条件があります。たとえば、以下のような条件です。
・借金の総額が収入や財産の価値を大きく上回っていること。
・借金の原因が不運や事故などであって、故意や不正な行為ではないこと。
・借金の返済が困難であることを証明できる資料や証人があること。
・過去10年以内に自己破産をしたことがないこと。
自己破産が出来ない場合
前述のとおり自己破産とは、借金の返済が困難になった場合に、裁判所に申し立てをして、借金の免責を受けることができる制度です。
自己破産をすると、ほとんどの借金がなくなり、新たな人生をスタートすることができます。
自己破産には一定の条件があり、それを満たさない場合は、自己破産ができないかもしれません。
自己破産できない事例は以下のような場合です。
支払い不能の状態でない場合
支払い不能とは、現在もしくは将来的に、借金の返済が不可能であることを意味します。
つまり、収入や資産があっても、借金の額がそれらを上回っている場合に、支払不能と判断されます。
支払不能であるかどうかは、裁判所が判断します。借金の額や内容、資産や収入の状況などが考慮されます。
一般的には、借金の額が年収の3倍以上である場合や、月々の返済額が収入の3分の1以上である場合は、支払不能とみなされやすいです。
しかし、支払不能の状態でない場合は、自己破産が出来ないのでしょうか?
答えは、必ずしもそうではありません。
実は、支払不能でなくても、自己破産が認められる場合があります。それは、支払困難の状態である場合です。
支払困難とは、現在もしくは将来的に、借金の返済が困難であることを意味します。
つまり、収入や資産があっても、借金の額に比べて不十分である場合に、支払困難と判断されます。
ただし、以下のような場合には支払い困難とは認められない可能性があります。
・借金の原因がギャンブルや浪費などの不正当な目的である場合。
・借金の返済を逃れるために故意に収入や資産を隠したり減らしたりした場合。
・借金の返済能力があるにもかかわらず、任意整理や債務整理などの他の方法を試さなかった場合。
・借金の返済能力があるにもかかわらず、生活水準を下げたり節約したりしなかった場合。
このような場合は裁判所が、自己破産を認めない判断をする可能性があります。
予納金が支払えない場合
予納金とは、自己破産の手続きにかかる費用の一部を、あらかじめ裁判所に納めることをいいます。
予納金は、破産手続開始の要件であり、支払わなければ自己破産はできません。
では、予納金はいくら必要なのでしょうか?
予納金には、以下の4種類があります。
・手数料
・官報公告費
・郵券
・引継予納金
手数料
は、自己破産の申し立てにかかる手数料で、収入印紙で納付します。
金額は1,500円です。
官報公告費
は、自己破産の開始決定や免責許可決定を官報に公告するための費用です。
官報公告は、債権者や社会に対して自己破産の事実を知らせるために必要です。
金額は10,000円から19,000円程度です。
郵券
は、債権者への通知や書類の送付などに必要な郵便切手です。
金額は5,000円程度です。
引継予納金
は、破産管財人の報酬や実費などに充てられる費用です。
破産管財人は、破産者の財産の調査や処分などを行う人です。
引継予納金は、管財事件と呼ばれる場合に必要であり、同時廃止事件と呼ばれる場合には不要です。
管財事件と同時廃止事件の違いについては後述します。
引継予納金の金額は裁判所によって異なりますが、一般的には20万円から30万円です。
以上の4種類の予納金を合計すると、同時廃止事件では2万円前後、管財事件では22万円から32万円程度が必要になります。
職業制限にて対応できない場合
職業制限とは、自己破産をしたことで一定期間、特定の職業や資格に就くことができなくなることです。
これは、他人の財産や秘密を扱う職業に就いている人に対して、信用や信頼を保つために設けられています。
【自己破産で制限される職業・資格】
・弁護士 ・司法書士 ・行政書士
・弁理士 ・宅地建物取引士 ・不動産鑑定士
・公認会計士 ・税理士 ・社会保険労務士
・公証人 ・銀行・信用金庫・日本銀行などの役員
・保険会社・貸金業者・質屋などの登録者や役員
・警備業者や警備員 ・公正取引委員会や教育委員会の委員
・人事院の人事官 ・旅行業者や旅行業務取扱者
・廃棄物処理業者 ・風俗業管理者 ・調教師・騎手
これらの職業や資格に就いている人は、自己破産をすると一時的に登録や免許が取り消されたり、解任されたりします。
その間は仕事に就くことができません。
では、この制限はいつまで続くのでしょうか?
一般的には、自己破産の手続きが終わって免責許可決定が確定するまでです。
免責許可決定とは、裁判所が債務者に対して債務を免除することを認める決定です。
この決定が出れば、債務者は復権します。復権とは、自由に仕事に就ける権利を回復することです。
免責許可決定が出るまでの期間は、申し立てから平均して4~6ヶ月程度です。
免責不許可事由に該当する場合
免責不許可事由に該当すると、自己破産をしても借金の返済義務が残ります。
そのため、自己破産を考えている人は、免責不許可事由について知っておく必要があります。
では、具体的にどのようなケースが免責不許可事由に該当するのでしょうか。
破産法によると、以下の11項目が免責不許可事由として定められています。
1. 財産を隠したり他人にあげたりした場合
2. 不利な条件で借り入れし返済を行った場合
3. クレジットカードの現金化を行った場合
4. 浪費により債務が拡大した場合
5. 賭博により債務が拡大した場合
6. 射幸行為により債務が拡大した場合
7. 詐術による信用取引を行った場合
8. 業務帳簿隠滅等の行為をした場合
9. 虚偽の債権者名簿提出行為をした場合
10. 調査協力義務違反行為をした場合
11. 管財業務妨害行為をした場合
これらの項目は、いずれも債権者(借金を貸している人や会社)の利益を損なうような行為や、自己破産することを前提に不正な借金をするような行為です。
このような行為は、自己破産制度の趣旨に反するものであり、同情や救済の余地がないと考えられています。
![]()
自己破産には種類があります

自己破産は大きく分けて3種類あります
自己破産にはいくつかの種類があり、それぞれに違いがあります。
この記事では、自己破産の中の、同時廃止、管財事件、少額管財の違いについて説明します。
同時廃止とは
自己破産の同時廃止とは、破産手続きが開始されると同時に終了することをいいます。
通常、自己破産では、裁判所から選任された管財人が債務者の財産を調査し、換価して債権者に配当します。
また、債務者が免責されるかどうかも審査されます。このような手続きを「管財事件」と呼びます。
しかし、債務者が一定額以上の財産を持っていない場合や、免責不許可事由がない場合は、管財人を選任する必要がありません。
また、債権者に配当することもできません。
そのため、裁判所は破産手続きを省略して廃止することができます。これが「同時廃止」と呼ばれる手続きです。
自己破産の同時廃止になる条件は次の3つです。
・個人の破産であること
・一定額を超える財産がないこと
・免責不許可事由がないこと
一定額という基準は裁判所によって異なりますが、20万円~30万円程度だと考えられます。
この額以下であれば、債権者への配当や管財人への報酬などの支払いができません。そのため、財産を処分する必要がありません。
破産手続開始決定と同時に、同時廃止の決定が下されればその時点で、借金の返済は免除されます。
管財事件とは
管財事件とは、自己破産を申し立てた人に一定額以上の財産がある場合に、その財産を裁判所が選任した破産管財人という専門家に管理させて、現金化して債権者に分配する手続きです。
また、破産者に免責不許可事由がある場合や債務額が多い場合などにも、免責の可否を調査するために管財事件となることがあります。
管財事件となると、同時廃止事件という費用や時間のかからない手続きよりも、手間やコストがかかります。
まず、裁判所に予納金という形で50万円から100万円程度のお金を納めなければなりません。
これは、破産管財人の報酬や手数料などをまかなうためのものです。また、管財事件は半年から1年ほどの期間をかけて進められます。
その間、破産者は自分の財産や生活状況などについて破産管財人や裁判所から質問されたり、郵便物が破産管財人に届いたりすることがあります。
さらに、旅行や引っ越しをするときなどには裁判所の許可が必要になることもあります。
したがって、自己破産をする場合はできるだけ同時廃止事件として処理されるようにしたいものです。
そのためには、事前に弁護士に相談して、自分の保有する財産や債務の状況を把握し、適切な対策を立てることが大切です。
弁護士に依頼すれば、少額管財事件という予納金が安く済む方法や、同時廃止事件への振り分け基準を知っているため、手続きをスムーズに進めることができます。
少額管財とは
管財事件の中でも、少額管財という特別な手続きがあります。
少額管財とは、以下の条件を満たす場合に適用される手続きです。
・債務者が個人であること
・債務者の資産が100万円以下であること
・債務者の債権者が10人以下であること
・債務者に免責不許可事由がないこと
少額管財のメリットは、通常の管財事件よりも手続きが簡略化されることです。
具体的には
・裁判所へ支払う予納金(引継予納金)が20万円程度で済むこと(通常は50万円以上)
・手続き期間が2~3ヶ月程度で済むこと(通常は半年~1年以上)
・債権者集会や免責審尋などの面倒な手続きが省略されること
などが挙げられます。少額管財を利用することで、早くて安く自己破産を終わらせることができます。
ただし、少額管財を利用する際には注意点もあります。
少額管財を運用している裁判所は限られています。
東京地方裁判所や大阪地方裁判所などでは運用されていますが、全国的に見るとまだまだ少数派です。
そのため、自分の住んでいる地域の裁判所が少額管財を運用しているかどうか事前に確認する必要があります。
![]()
自己破産後の生活はどうなる
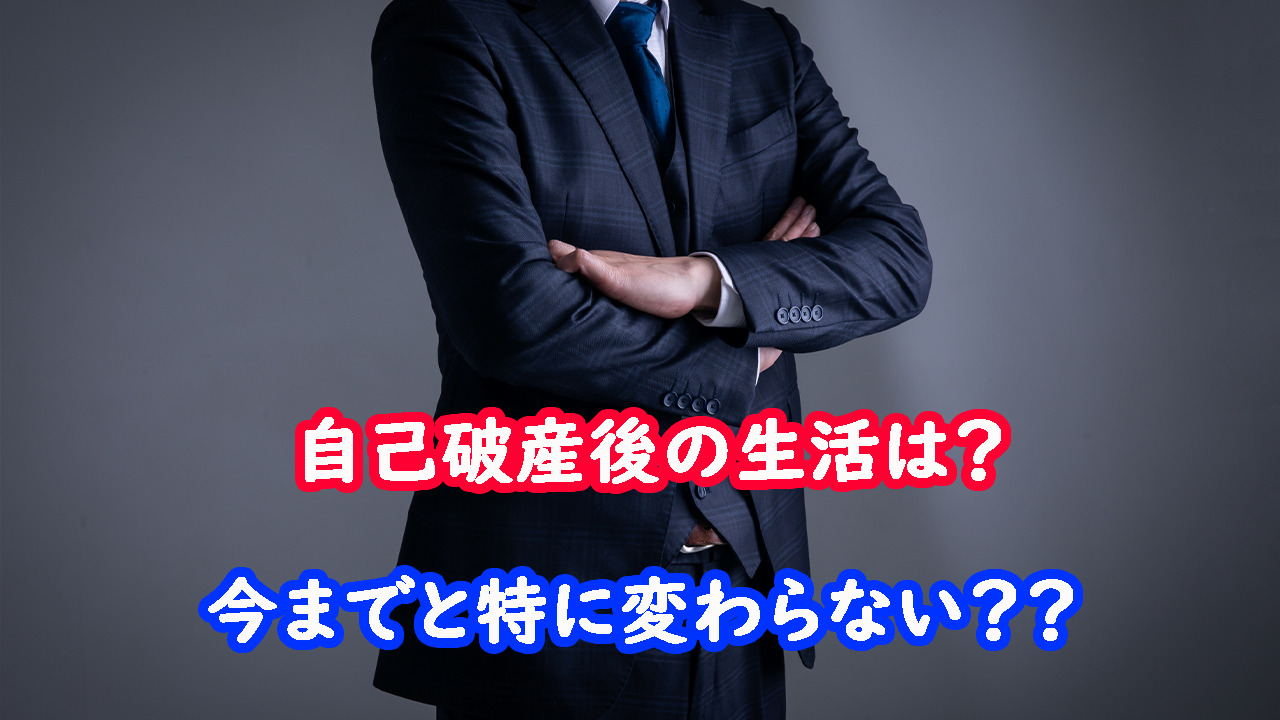
自己破産後の生活のメリット
自己破産後の生活について、具体的にどうなるのかを解説します。
自己破産後のメリットとして、以下の3つが挙げられます。
1.借金から解放される
2.経済的な余裕が生まれる
3.精神的な安心感が得られる
1.借金から解放される
自己破産の最大のメリットは、借金から解放されることです。
自己破産によって、免責不許可事由に該当しない借金はすべて免除されます。
つまり、返済義務がなくなります。これは、他の債務整理手続きでは得られない特権です。
借金がなくなれば、債権者からの取り立てや督促もなくなります。
借金に苦しんでいた人にとって、これは大きな救いとなるでしょう。
2.経済的な余裕が生まれる
借金から解放されれば、返済に回していたお金が手元に残ります。
これによって、経済的な余裕が生まれます。
生活費や貯金に充てることができますし、必要な支出や投資もできるようになります。
また、自己破産後は新たな借金をすることができませんが、これは逆に無理な借入を防ぐことにもつながります。
自己破産後は、収入と支出のバランスを考えた賢いお金の管理をすることが大切です。
3.精神的な安心感が得られる
借金から解放されることで、精神的な安心感も得られます。
借金によってストレスや不安を感じていた人は多いでしょう。自己破産後は、その重圧から開放されます。
心にゆとりが生まれれば、人間関係や仕事にも前向きに取り組めるようになります。
また、自己破産は債務者の生活再建を目的とした手続きです。自己破産後は、新たな人生のスタートと捉えて、将来の目標や夢を持つことができます。
以上が、自己破産後のメリットです。
自己破産後の生活のデメリット
自己破産には、借金から解放されるという大きなメリットがありますが、一方でデメリットもあります。
自己破産後の生活にどのような影響があるのか、以下にまとめてみました。
1.財産を失う
2.信用情報に傷がつく(ローンやクレジットカードが作れなくなる)
3.官報に掲載される
4.資格や職業に制限がかかる
5.保証人や連帯保証人に迷惑をかける
大きく5つあります。
1つずつ見ていきましょう。
1.財産を失う
自己破産をすると、生活に必要な最低限の財産を除いて、すべての財産を手放さなければなりません。
具体的には、時価20万円以上の財産(家や車など)や99万円を超える現金は処分されます。
これらの財産は、債権者に分配されるため、自己破産後に取り戻すことはできません。
2.信用情報に傷がつく(一定期間ローンを組む、クレジットカードが作る。が出来なくなる)
自己破産をすると、信用情報機関に金融事故情報が登録されます。
これはいわゆる「ブラックリスト」に載るということです。
ブラックリストに載ると、新たな借入やローン、クレジットカードなどの契約ができなくなります。
また、賃貸契約や就職活動などでも信用情報が確認されることがありますので、不利になる可能性があります。
ブラックリストから抹消されるまでには、5年から10年程度かかると言われています。
3.官報に掲載される
自己破産をすると、裁判所の公告として官報に個人情報が掲載されます。
官報は政府情報の公的な伝達手段であり、インターネットからも閲覧できます。
官報に掲載される個人情報には、氏名や住所、生年月日、職業などが含まれます。
このように個人情報が公開されることは、プライバシーの侵害や社会的信用の低下につながる恐れがあります。
4.資格や職業に制限がかかる
自己破産をすると、一部の資格や職業に就くことができなくなります。
これは自己破産手続き中だけでなく、免責後も一定期間続く場合があります。
制限を受ける資格や職業の例としては、弁護士や公認会計士、社会保険労務士などの法律系資格や、旅行業者や警備員などの営業許可系資格が挙げられます。
また、公務員や金融機関などでも採用されにくくなる可能性があります。
5.保証人や連帯保証人に迷惑をかける場合がある
自己破産をすると、保証人や連帯保証人にも大きな影響が及びます。
保証人や連帯保証人とは、借金をした本人(主債務者)が返済できなくなった場合に、代わりに債権者(貸した人)に返済する役割を担う人のことです。
保証人や連帯保証人は、親族や友人などの信頼関係のある人がなることが多いです。
しかし、主債務者が自己破産をすると、保証人や連帯保証人は次のような問題に直面する可能性があります。
・債権者から借金の一括請求をされる
・主債務者から返金を請求できなくなる
・ローンの一括返済の請求をされる
このような事が保証人、連帯保証人にかかってきます。
自己破産を選択する場合、弁護士や司法書士の先生に正直に全ての債務を話して、出来るだけ他人に迷惑をかけないような方法を相談しましょう。
しかし、保証人のいない借金しかない場合は、このような事にはなりません。
![]()
自己破産後の生活は、意外とダメージが小さい
今まで自己破産についてザックリと説明してきましたが、意外にデメリットは少ないと感じた方も多いのではないでしょうか。
実際、普通のサラリーマンの方だったら
・5~10年ローンを組みにくくなる。
・クレジットカードが作れなくなる。(5~10年)
位の影響はありますが、それと引き換えに
・借金が無くなる。
・取り立ての電話や、督促状が来なくなる。
・新しい人生を歩む事ができる。
といった具合に、人生の再チャレンジを行えます。
そこで10年程かけて、信用を回復し、新たにローンを組めたり、クレジットカードを作ったりする事は十分に可能です。
本当に精神的に追い込まれるような状態にまで、借金が多くなってしまった場合には、自己破産も選択肢の中に入れて、専門機関に相談しましょう。
![]()
まとめ
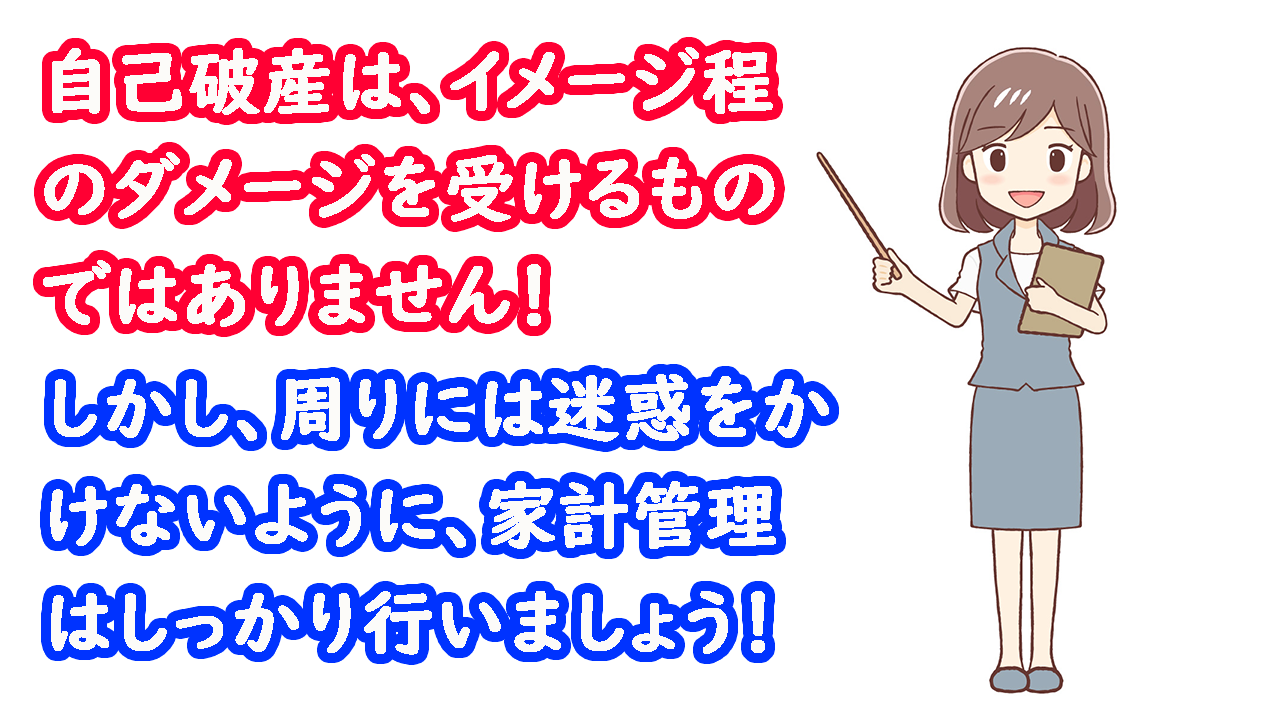
借金に悩む事は辛いので、悩むなら専門家に早めの相談を!
いかがだったでしょうか。
今回は、自己破産とはどういうものなのか?
自己破産後の生活はどうなってしまうのか?
に焦点をあてて書いてみました。
記事タイトルにもある通り、自己破産後の生活は、特に今までと変わりなく過ごしていけるだろうと思います。
だけど、同じ失敗を繰り返さないように、借金癖やギャンブル癖のある方は、家計管理をしっかり行っていく事は忘れてはいけませんね。
家計簿アプリを利用する事で、家計の管理がかなり楽になるのでおすすめです。
参考にして頂けると嬉しいですね❢
今回も皆様のお役に立てたら幸いです!
次回も役立つ情報を発信出来るように頑張りますので、よろしくお願いいたしますm(__)m
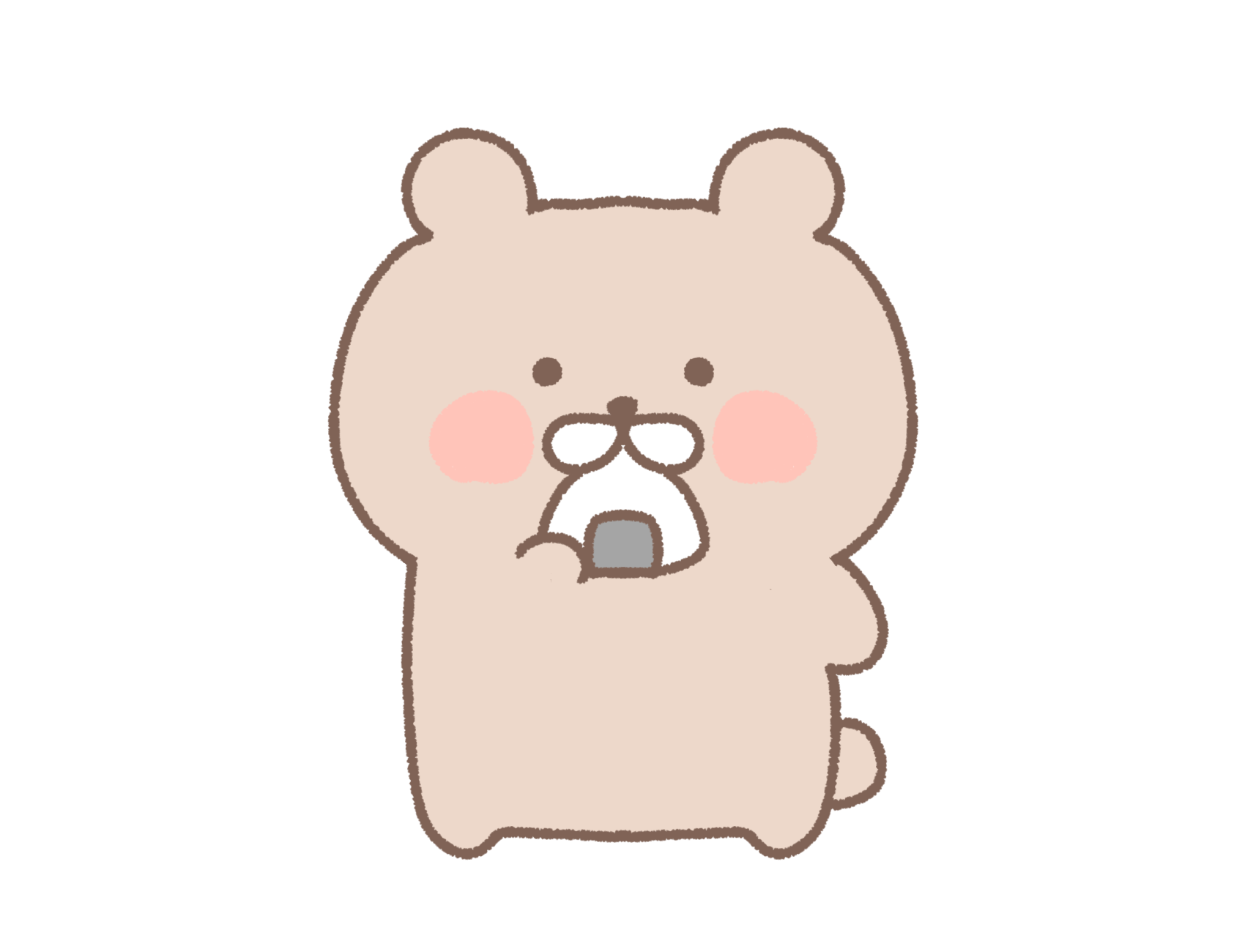


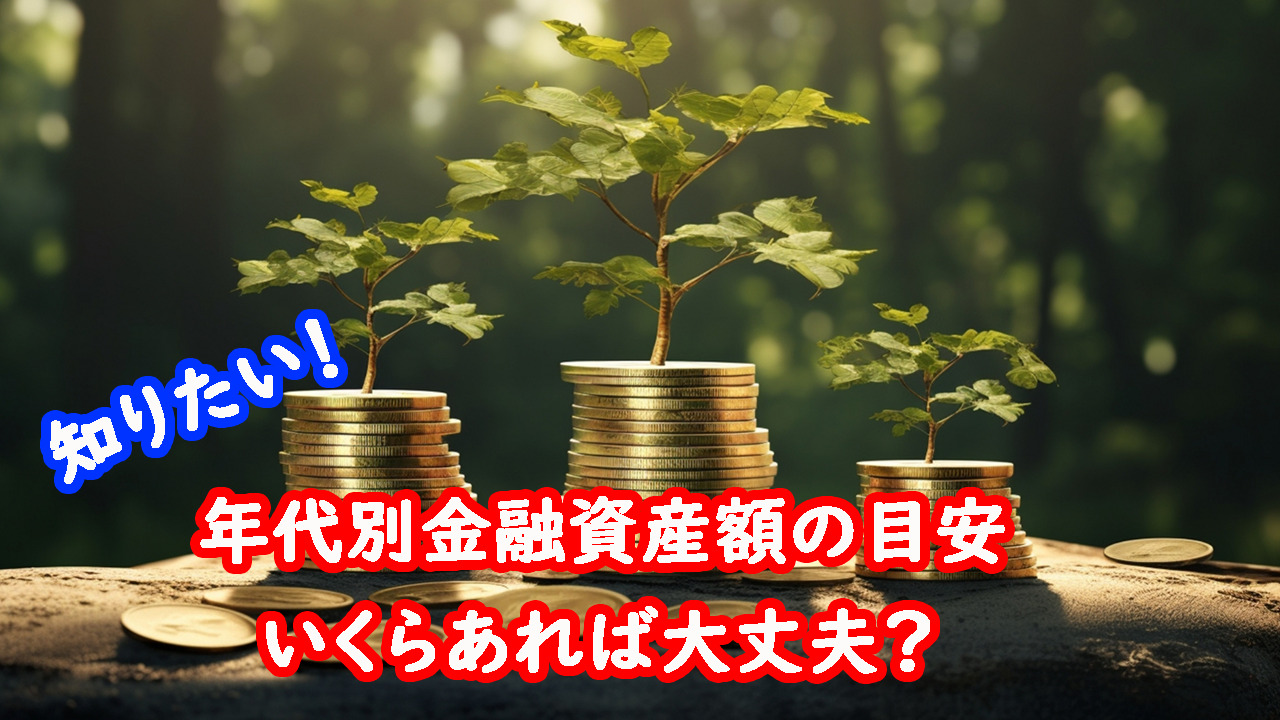

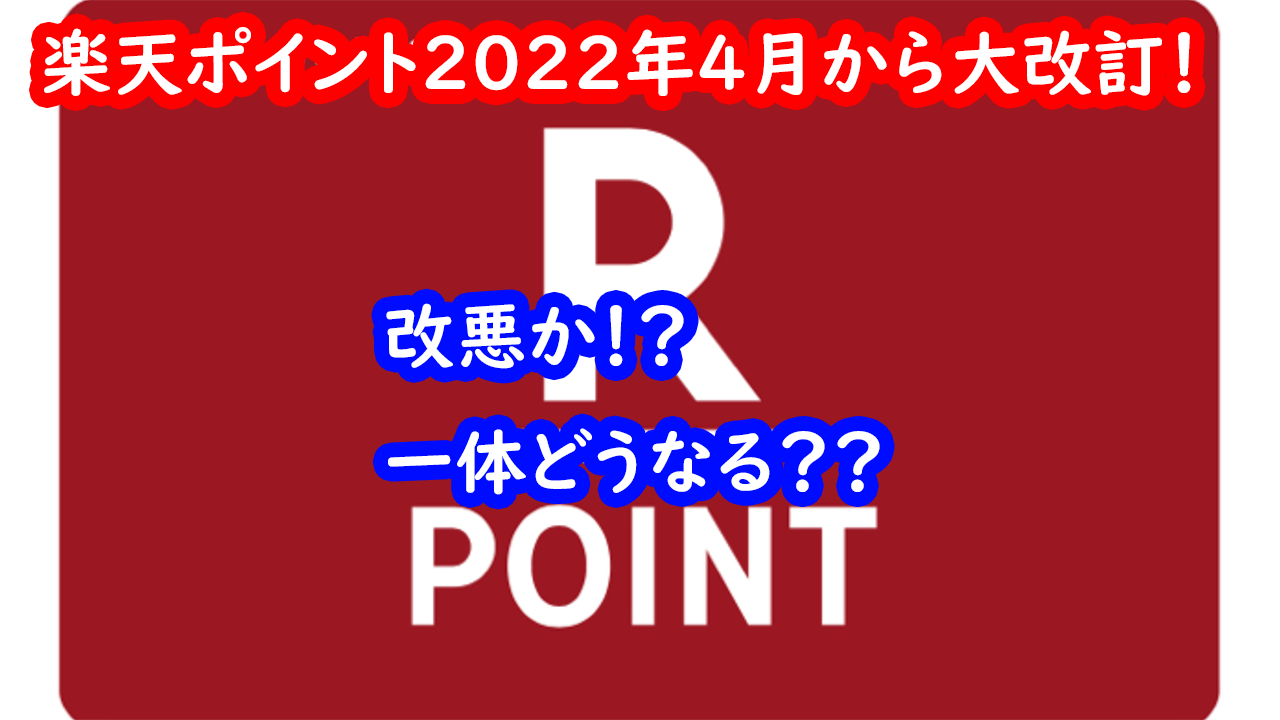

が誕生! キャッチ画像.png)